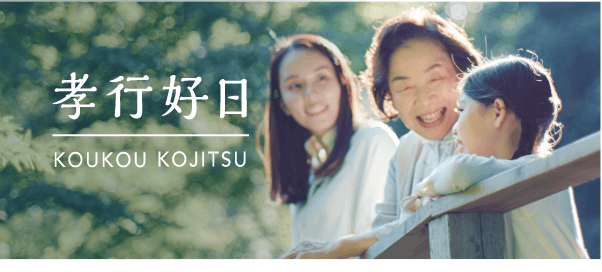お墓各部の名称について(4) 神道墓と各部の呼称。
皆様こんにちは。
「お墓の加登」広報スタッフブログ「カトカト日記」をいつもご覧いただきありがとうございます。
今日は「お墓各部の名称について」の第4弾ということで、神道のお墓(神道墓、神徒墓)についてご説明したいと思います。
写真は当ホームページ「墓石のカタチやデザイン、各部の名称を徹底解説」ページに掲載している神道のお墓です。
いわゆる仏式のお墓とは形状が少々異なるのがお分かりでしょうか。

すぐに目につくのが、棹石(竿石、軸石)の頂上部が尖っている点ですね。
ピラミッドのような四角錐形をしており、これを兜巾(ときん)と呼びます。
三種の神器として有名な『草薙の剣(くさなぎのつるぎ。正式には「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」』を模した形状であるとも言われています。
棹石は上部にいくほど細くなっていくことも多いのですが、こちらの写真のように棹の太さが上下で変わらないものもあります。

ちなみに「兜巾(ときん)」というのは元々修験道(しゅげんどう)の山伏の被る帽子のことです。

神道ではお焼香をしないため、お墓には香炉や線香立てがありません。
また、仏式のお墓における供物台(くもつだい)の役目を果たすのが「八足台(はっそくだい)」です。

神道のお墓の特徴としてもうひとつ挙げられるのが、墓石に刻む文字です。
仏式では、棹石の表に「南無阿弥陀佛」のような各宗派のお題目か「○○家之墓」などを刻むのが一般的ですが、神式では「○○家之奥都(津)城」などと刻まれます。
「奥都(津)城」は「おくつき」と読み、上代にはお墓のことを表す語だったのが、後に転じて神道のお墓のことを指すようになりました。

厳密に言うと、一般の信徒の場合には「津」の字を用いて「奥津城」と書き、神官や氏子(うじこ)の場合に「都」の字を用いるそうですが、現在ではさほど厳密に定められてはいません。
また、仏教でいう戒名はなく、「神号(霊号、霊神号、霊名とも)」といって生前の姓名の下に尊称(諡名=おくりな。「之霊」「命」「命霊」「霊位」「大人」「刀自」「比古」「郎女」「童子」「若子」など)をつけたものを墓石または墓誌に刻みます。
以上、本日は神道のお墓についてでした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました!
一緒に読んでほしいブログ



まずはお気軽に資料請求・
ご相談ください。