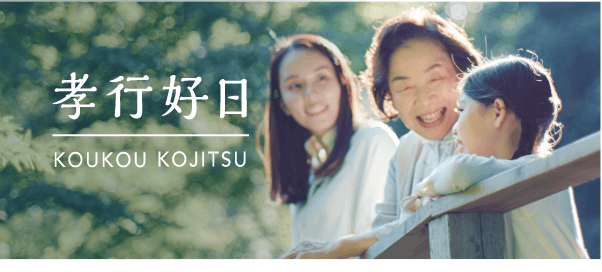昔の墓石とお墓の歴史(1) 層塔(そうとう)。
本日も加登の広報スタッフブログ「カトカト日記」をご覧いただきありがとうございます。
先日、奈良県桜井市の長谷寺(はせでら)さんと談山神社(たんざんじんじゃ)さんに紅葉狩りに行ったのですが、いずれの境内にも素晴らしい「層塔(そうとう)」があったので、今回は層塔についてご紹介したいと思います。

平成28年11月23日、談山神社にて。紅葉はもちろん、瞠目の鮮やかさでした!
「層塔」とは?
皆様、「層塔」という言葉はご存知でしょうか?
恐らく多くの方がピンと来ないと思いますが、「五重塔」とか「三重塔」なら耳にしたことがあるはずです。
層塔とは、屋根が幾層にも重ねられた仏塔の総称なのです。
こちらは長谷寺の五重塔です。
それぞれの屋根には「五大思想」という仏教的宇宙観が反映されていて、下から順に地、水、火、風、空といった
意味が当てられています。
「五輪塔(ごりんとう)」というお墓と似た構造ですね。

平成28年11月23日撮影。紅葉のピークは過ぎていたようですが、それでもまだまだ楽しめました。
「層塔」のはじまり
こちらは同じく長谷寺さんにある「道明上人御廟(どうみょうしょうにんごびょう)」です。
道明上人は、朱鳥元年(686年)に「本長谷寺」を西の岡に建立した方です。
後に徳道上人が東の岡に後長谷寺を建立し、さらに時代が下りふたつがひとつとなって現在の長谷寺となったという説があります。

どちらかと言えば木造のイメージが強い「層塔」ですが、このような石塔タイプも多数残っており、意味合いとしては木造も石塔も同じです。
奈良時代以降、仏教の普及とともに、貴族や高僧のあいだで墓石が建てられるようになりました。
既に奈良時代の初めには、層塔と呼ばれる石造りの塔が建てられていました。
石で造ることによって、より身近になった仏塔の中に、貴族たちは経文(きょうもん)などを納め祈ることで現世あるいは来世における救済を願ったのです。

層塔の構造
長谷寺から車で20分ほど走ると、有名な「談山神社(たんざんじんじゃ)」さんがあります。
中臣鎌足(後の藤原鎌足)が中大兄皇子(後の天智天皇)とともに、この地で大化の改新を画策したとされる神社です。
元々はお寺だったそうで、境内には木造の見事な十三重塔があります。

見れば見るほど味わい深い塔でした。
全貌がレンズに収まり切らなかったため、一部しかお見せすることが出来ないのが残念ですが、紅葉と見事に調和してそれはもう圧巻でしたよ。
層塔の屋根の数は奇数が原則で、石造りの層塔は三、五、七、九、十三重など様々ですが、木造の殆どは三重塔か五重塔で、十三重塔はわが国で唯一談山神社にしかないのだとか。

層塔の頂上部には「相輪(そうりん)」が天に向かって聳えています。
相輪は7つの部分から構成されており、上から順に宝珠(ほうしゅ)、竜車(りゅうしゃ)、水煙(すいえん)、宝輪(ほうりん)、請花(うけばな)、伏鉢(ふせばち)、露盤(ろばん)と呼ばれます。
一番上に設置された宝珠は仏舎利(ぶっしゃり。お釈迦様のお骨)を納めるためのもので、相輪の中でも最も重要な位置を占めます。

数えてみると、12層は写っています。あと少しで13層だったのね。
いかがだったでしょうか?
長谷寺さんには宝篋印塔もあったので、そちらについても近々記事にしたいと思います。
お楽しみに!
まずはお気軽に資料請求・
ご相談ください。